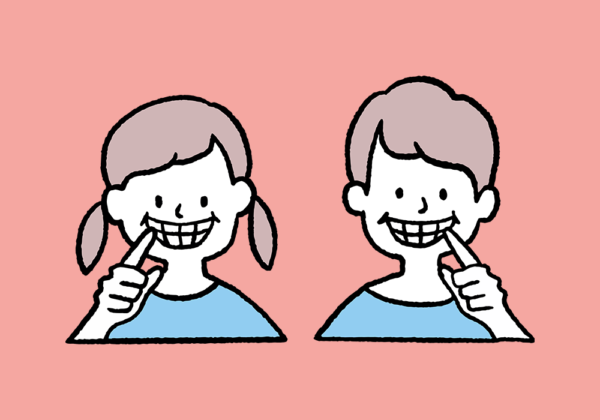口呼吸を防いで歯周病を予防しよう

こんにちは。我孫子中央歯科室です。
皆様は、口呼吸が歯ぐきの健康に深く関わっていることをご存じでしょうか?
口呼吸の習慣がある方は、お口の中が乾燥しやすくなり、歯周病が悪化するリスクが高まります。
今回は、口呼吸と歯周病の関係、そして効果的な予防法についてお話しします。
口呼吸がもたらす歯周病リスクとは?
口呼吸の場合、お口の中が乾燥しやすくなり、唾液の分泌量が減少します。
唾液には細菌の繁殖を抑えてお口の中を清潔に保つ役割がありますが、唾液の量が減ってしまうと細菌が繁殖しやすくなり、歯ぐきの炎症や歯周病のリスクが高まります。
また、口呼吸によって舌の位置が下がると歯並びが乱れる可能性があり、結果として歯みがきが行き届きにくくなり、歯周病になりやすくなる恐れもあります。
無意識に口呼吸になっていませんか?
無意識に口呼吸になっていないか、次のチェックリストで確認してみましょう。
- お口が開いていることが多い
- いびきをしているといわれる
- 唇がよく乾燥し、荒れやすい
- 鼻が詰まりやすい
この中で複数当てはまる場合は、口呼吸が習慣になっている可能性があります。
日常生活の中でできる口呼吸の予防法
お口の周りの筋肉を鍛える体操
お口の周りの筋肉が弱いと、自然とお口が開いてしまいます。
「あ・い・う・え・お」と大きくお口を開けて発声することで、口輪筋を鍛えましょう。
飲酒を控える
寝る前の飲酒は、気道を広げる筋肉が緩んだり、鼻が詰まりやすくなるため口呼吸を助長します。飲酒をする場合は、適量を守るよう心掛けましょう。
就寝時に「口テープ」を活用する
睡眠中にお口が開いてしまうのを防ぐために、専用の「口テープ」を貼る方法があります。
テープを軽く貼ることで、お口が開くのを抑え、鼻呼吸を促すことができます。
ただし、無理に貼ると苦しく感じることがあるため、慣れるまでは様子を見ながら調整しましょう。
自宅でできる予防
正しい歯みがきを習慣にする
歯と歯ぐきの境目にブラシを当て、小刻みに動かしながらみがきましょう。
また、デンタルフロスや歯間ブラシを使うと、歯と歯の間の汚れを効果的に落とすことができます。
歯ぐきを強くする食生活を意識する
ビタミンCはコラーゲンの合成を促進する働きがあり、壊れた繊維の再生にも役立ちます。赤パプリカやアセロラなど、ビタミンCを含む食品をバランスよく取り入れて、歯ぐきのを強くする生活習慣を意識しましょう。
歯科医院でできる予防
歯ぐきの状態を確認する
歯科医院では、歯ぐきの状態を詳しく確認し、問題がある場合は適切な処置をすぐに行います。
自覚症状がない場合でも、定期的に歯科検診を受けて歯周病の早期発見や予防につなげることが大切です。
唾液検査で口腔環境を確認する
歯科医院では「唾液検査」を行なっているところもあります。唾液の分泌量や細菌の種類・バランスを調べることができ、自分の口腔環境を知ることができます。
さらに、検査結果に基づいて適切な予防やケアを行うことで、より効果的に歯ぐきを守ることにつながります。
まとめ
口呼吸の習慣があると、歯周病のリスクが高まります。
さらに、口呼吸による乾燥は、細菌の増殖を助長し、歯ぐきの炎症を引き起こす原因になります。
毎日のセルフケアをしっかりと行い、バランスの良い食事を心掛けることで歯ぐきの健康を守りましょう。
当院では、一人ひとりに合ったセルフケアのアドバイスなど、健康的な口腔環境の維持をサポートしています。気になる方はお気軽にご相談ください。